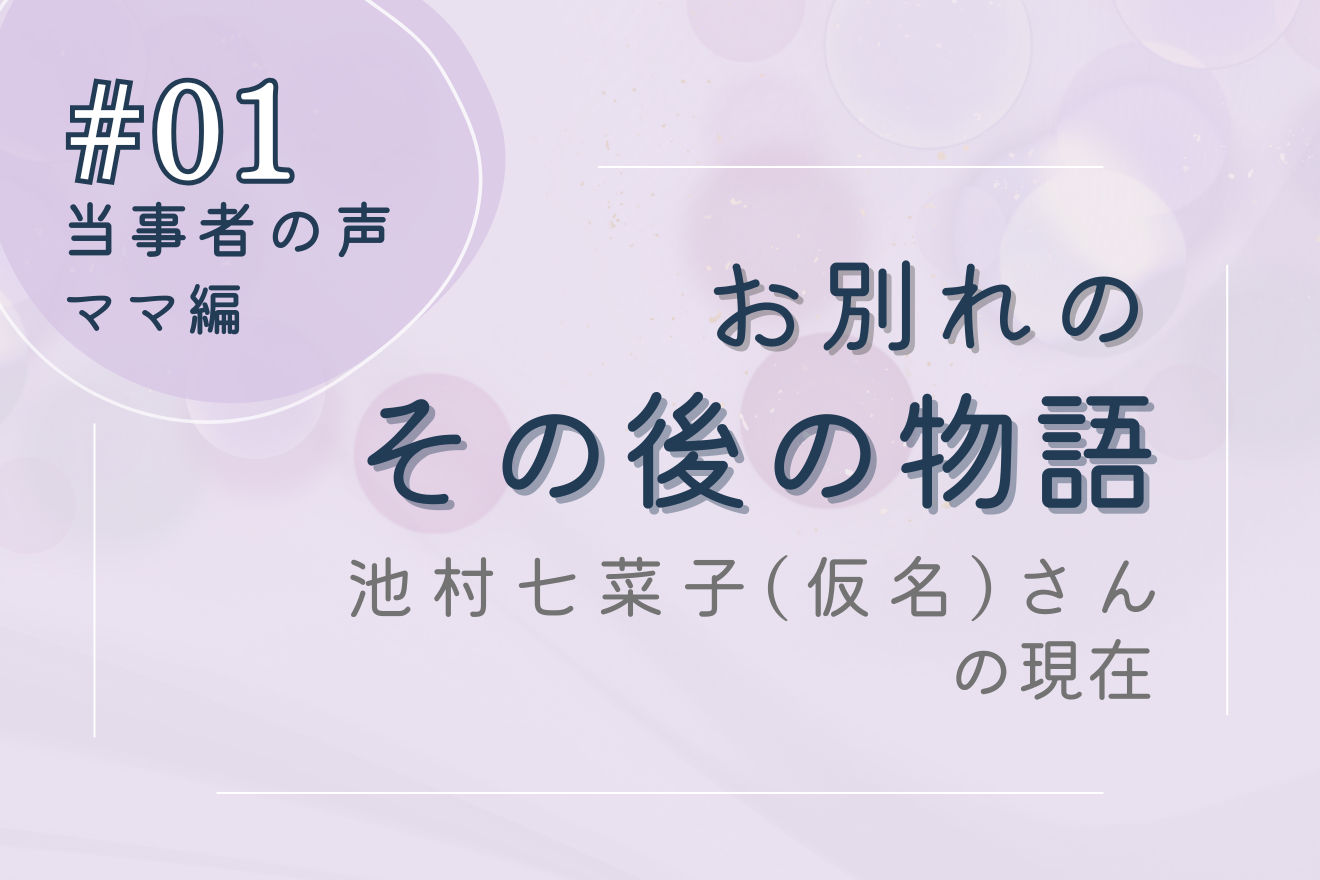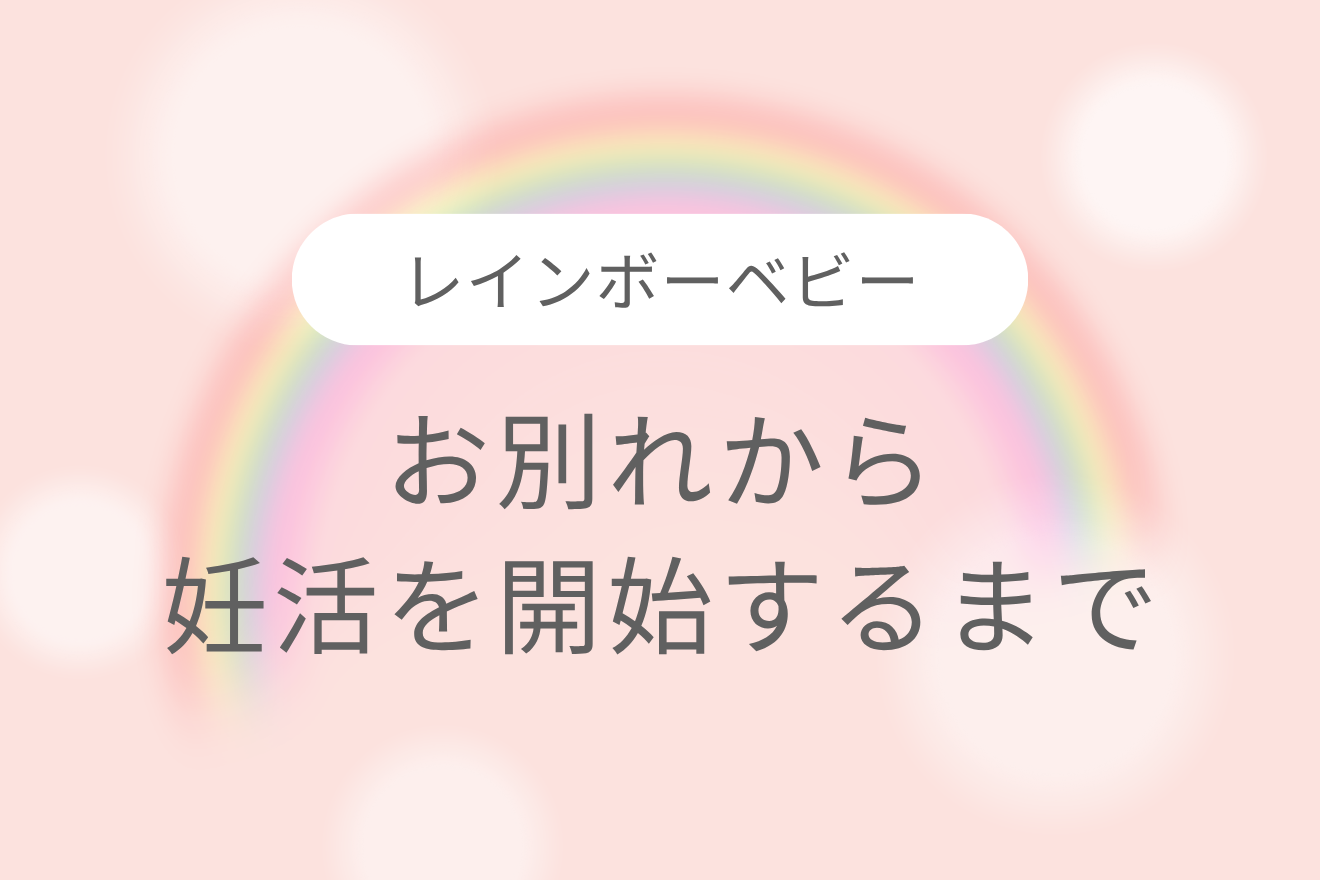私は、子どもと死別してから、切り離すことのできない十字架を背負ったような気持ちになることがある。家族という身近な存在が、いとも簡単に消えてしまうという恐怖を感じながら、日々感謝の気持ちを伝えることを忘れずに生きている。一方で、身近な存在とのお別れを経験したことが無い人を妬ましく、羨ましく思うこともある。この悲しみを、辛さを、死に対する重圧を感じずに生きられるなら、どれだけ良かったか。赤ちゃんを亡くすという経験をしたことで、自分は『周囲とは違う人間である』とレッテルを貼られたような孤独感があった。
子どもを亡くすという経験は、マイノリティである。しかし、最近はこう思うのだ。人間は生きる上で、身近な人との死別は遅かれ早かれ必ず経験するものだと。世間の大多数が、初めての死別を祖父母や親で経験するだろう。赤ちゃんとお別れをした私たちは、その経験が人より少し早く、それが我が子だったということなのだ。そう考えると、この経験はマイノリティだが、世間の人たちと同じ死別を経験した存在なのだと思い、心が軽くなった。
今回、インタビューに応じてくれた咲希さんは、切迫早産で超低出生体重児を出産している。何度も多くの苦難を乗り越えたが、生後1歳30日で突然のお別れとなってしまった。死別後、周囲の反応で心を痛めることが多くあったと語る。そんな時に、咲希さんが見つけた記事の中に、心を救ってくれる一文があったそうだ。
※この先センシティブな画像が含まれます。
生後1歳30日/急性胃腸炎による幼児死
名前:宇佐美咲希さん(仮名)
地域:東京都
職業:医療職(パート)
家族構成:ママ(44歳)、パパ(45歳)、お子さんがお空に1人
38歳で結婚し、すぐに不妊治療を開始した。体外受精のため採卵を4回、胚移植を6回繰り返し、第一子を授かる。子宮頸管無力症で早産となり、その後、生後1歳30日で急性胃腸炎を発症し幼児死となった。
寒空の下で
病院の外に出ると、冷え切った空気が肌を突き刺す。
「寒いからあたたかくして帰ろうね」
そう呟いて冷たくなりかけている我が子に、マフラーを巻いてあげた。昨日まで感じていた肌のぬくもりは返ってこない。雪の積もった歩道を避けながら、夫婦でベビーカーを押して帰路に就いた。凍りついた道が、まるで私たち家族のことを表しているようだった。
苦しみを乗り越えて
私たち夫婦は、38歳で結婚した。定期的に開催される同窓会で小学校からの同級生と意気投合し、気が付けば互いに惹かれ合っていた。
子どもが欲しかったため、がん検診のついでに妊娠能力を測るための検査をした。医師から自然妊娠は厳しいだろうと言われたため、すぐに不妊治療を開始した。
それから2年後。数えきれない痛みと苦痛を経験し、6回目の移植でようやく子どもを授かった。“陽性”と聞いた時は、正直耳を疑った。
本当に私がママになれるの?
喜びと戸惑いが入り交じった、そんな気持ちだった。
幸いなことにつわりも軽く、仕事を続けながら順風満帆な妊婦生活を送っていた。妊婦健診のときに、「咲希さん、すごい元気だからいいお母さんになるね」と言われたことが嬉しかったのを覚えている。これから迎えるであろう、明るい未来に想いを馳せる毎日だった。
小さな命の産声
妊娠23週の妊婦健診の日。
この日は朝から調子が悪かった。お手洗いに行くと少量の出血があり、いつもと違う下腹部の違和感もあった。何かが出たような感覚だった。そのまま病院へ向かい、エコーをしてもらうと、医師から「もう赤ちゃんの足が見えているので、このまま入院です」と言われた。頭の中で状況を整理する時間もなく、あれよあれよと言う間にMFICU(母体胎児集中治療室)へ運ばれた。
医師の説明によると、子宮頚管無力症で赤ちゃんが今にも生まれてきてしまいそうな状態だそうだ。既に赤ちゃんの足が見えているため、成功するかはわからないが、子宮口を縛る手術をするかどうかの選択を迫られた。23週で生まれたら、赤ちゃんにどんな合併症が起こるか、考えるだけでも胸が痛くなる。どうか、生きてほしい。藁にも縋る想いで、手術を受けることを決意した。
——そんな想いも虚しく、手術を受けた翌日に破水してしまった。緊急帝王切開となった。
身長30cm、体重630gの小さな命が、産声をあげて誕生した。
医師が予想していたより遥かに赤ちゃんの状態が良く、その場にいた全員が安堵した。生まれた我が子、結理の産声は、か細く小さいが確かに『生きている』と証明してくれた。
尽きることのない不安
結理は生まれてすぐにたくさんの管に繋がれ、NICU(新生児集中治療室)に入院となった。出産の翌日に急変したと連絡があり、医師から重度の脳室内出血を起こしていると告げられた。
「もう明日の朝は迎えられないと思ってください」
そんな……結理は生まれたばかりなのに。
喜びも束の間、絶望の淵に追いやられた。
その後、脳室内出血の影響で水頭症を併発し、呼吸窮迫症候群、未熟児網膜症、てんかんなど数えきれないほどの合併症を抱えたが、生死を彷徨うような大きな山場は乗り越えることができた。結理は強い子だ。この後も、合計4回の手術が待ち受けていたが、「きっと結理なら乗り越えられる」と我が子の生きる力を信じることにした。

在宅医療と小さな喜び
4回の手術を乗り越え、生後7ヶ月になる頃。まだ胃管は入っているが、状態が落ち着いてきていたため、退院することができた。
最初のうちは、胃管からミルクを注入したり、酸素の数値を確認しながら酸素投与量を調整したり、慣れないことが多かったが、訪問診療の医療者の力を借りてお世話することができていた。哺乳瓶の乳首を口元に当てても咥えることはなかったが、ミルクを流し込んでゴックンと飲んでくれた時は心から嬉しく感じた。
生後10ヶ月になる頃には、離乳食も検討し始め、少しずつ結理のペースで成長していく様子を見守っていた。
ただ過ぎていく光景
1歳の誕生日を迎え、いつもと変わりない日々を過ごしていた。
その日はいつも通り、ミルクを飲ませて、薬をあげた。
ふと、結理の様子がいつもと違うことに気がつく。酸素や脈拍を測るモニターを見ると、いつもより脈拍が早かった。熱を測ると39度あり、慌てて解熱剤を飲ませた。
しばらく様子を見たが、解熱することはなかった。かかりつけの大学病院へ連絡し、11時頃に外来を受診した。看護師から「このまま入院になるだろうから、お父さんと交代でお昼を食べて、荷物の用意をしてきてください」と言われ、私たちは言われるがままに対応した。看護師の言っていた通り、14時頃に入院となった。
結理は、下痢や嘔吐をしており、依然として熱も下がっていなかった。
辛いよね、苦しいよね。頑張れ、結理——。
心の中で祈っていると、看護師がバタバタと走って部屋に入ってきた。「心拍が聞こえません。お母さん外に出てください!」そこから先の記憶はほとんどない。目の前の出来事が現実か夢なのかも判断がつかないくらい、ただただ周りの目まぐるしい光景を眺めることしかできなかった。
——19時。死亡確認がされた。
私たちの子だから大丈夫
当時を振り返り、咲希さんはこう語る。
「今回もきっと頑張ってくれる。なんだかんだ言っても、大丈夫。だって私たちの子だから」夫婦揃って、そう思っていました。朝起きて気づいた時には熱があったので、正直いつから具合が悪かったのかがわからないんですよね。もしかしたら、もっと早い時間に具合が悪くなっていたのかもしれない。早く気づいてあげられたら良かったのに、と今でも思っています。
取り残される感覚
結理とお別れをして、数ヶ月が経ち、私は職場復帰することになった。
職場の人たちは、気兼ねするような間柄ではなく、休日に公園に遊びに行くような仲の良い関係性だった。しかし、今の私と周囲の人たちには大きな温度差があった。
「この間のお休みどこ行った?」
「うちの子が⚪︎⚪︎でさ〜」
「学校の行事で⚪︎⚪︎が……」
私がいる場所で、子どもの話ばかりだ。もちろん、私が子どもを亡くしたことは、その場にいる全員が知っている。私が妊娠する前から、そういう話題ばかりだった気がする。それでも、子どもと死別したばかりの人の前で、気を遣ったりしないのだろうか。
そんな息苦しい毎日を送っていたら、私だけが周りから取り残されたような感覚になった。悲しい、悔しい、苦しい……次第に怒りの感情に変わる。このまま同じ職場では働けないと感じ、10ヶ月ほど休職したが、その後復帰せずに退職することにした。
納得できる心の在り方
咲希さんは、時間が経つにつれて様々な考え方ができるようになったと言う。そのきっかけの一つとして、とある記事の一文を紹介してくれた。
ある事件で子どもを亡くした母親が「子どもを亡くし、もがき苦しむ時間を味わったが、周りにいる人たちは、かける言葉が見つからない切なさを味わい、わかってあげられないもどかしさを感じていたことを忘れずにいたい」「未経験者の方は子どもを亡くした悲しみを感じることはできないのかもしれない。しかし、経験者である私もまた、未経験者が感じるもどかしさや切なさがどれほどなのかということを感じることはできない」と語っている記事を見ました。
この母親も、私と同じように苦しくて辛い時間を過ごしたはず。それなのに、他人と比較したり、自分は不幸だと僻んでばかりの私とは、全く違う考え方をしていました。この記事を読んで、少し自分の中で前向きに過ごせるようになりました。ひねくれた考えしか持てなかった私に、優しい光と前向きに生きていける気持ちをもたらしてくれたことに感謝しています。
赤ちゃんとお別れをした多くの当事者が、子どもとの死別以外の『心の痛み』を経験しているだろう。子どもを亡くした親、その家族みんなが生きやすい環境になることを願うが、今すぐに社会を変えることは難しい。
私たち当事者にできることは、咲希さんのような当事者の経験を知り、自分の中で様々な受け止め方を試してみることだ。傷つく環境から逃げてもいい、理解していない人に直接伝えてもいい、新しい捉え方を知って考え方を変えてもいい。正解はないが、不正解もないのだ。自分が納得できる心の在り方を見つけられることを願っている。
著者(写真=咲希さん提供/取材・文=SORATOMOライター 小野寺ゆら)
この記事は、2024年7月に取材した際の情報で、現在と異なる場合があります。
当事者の経験談を元に構成しており、同じお別れを経験した方に当てはまるものではありません。
不安な症状がある場合は、医療機関の受診をおすすめします。
※記事内の画像や文章の転用を禁じます