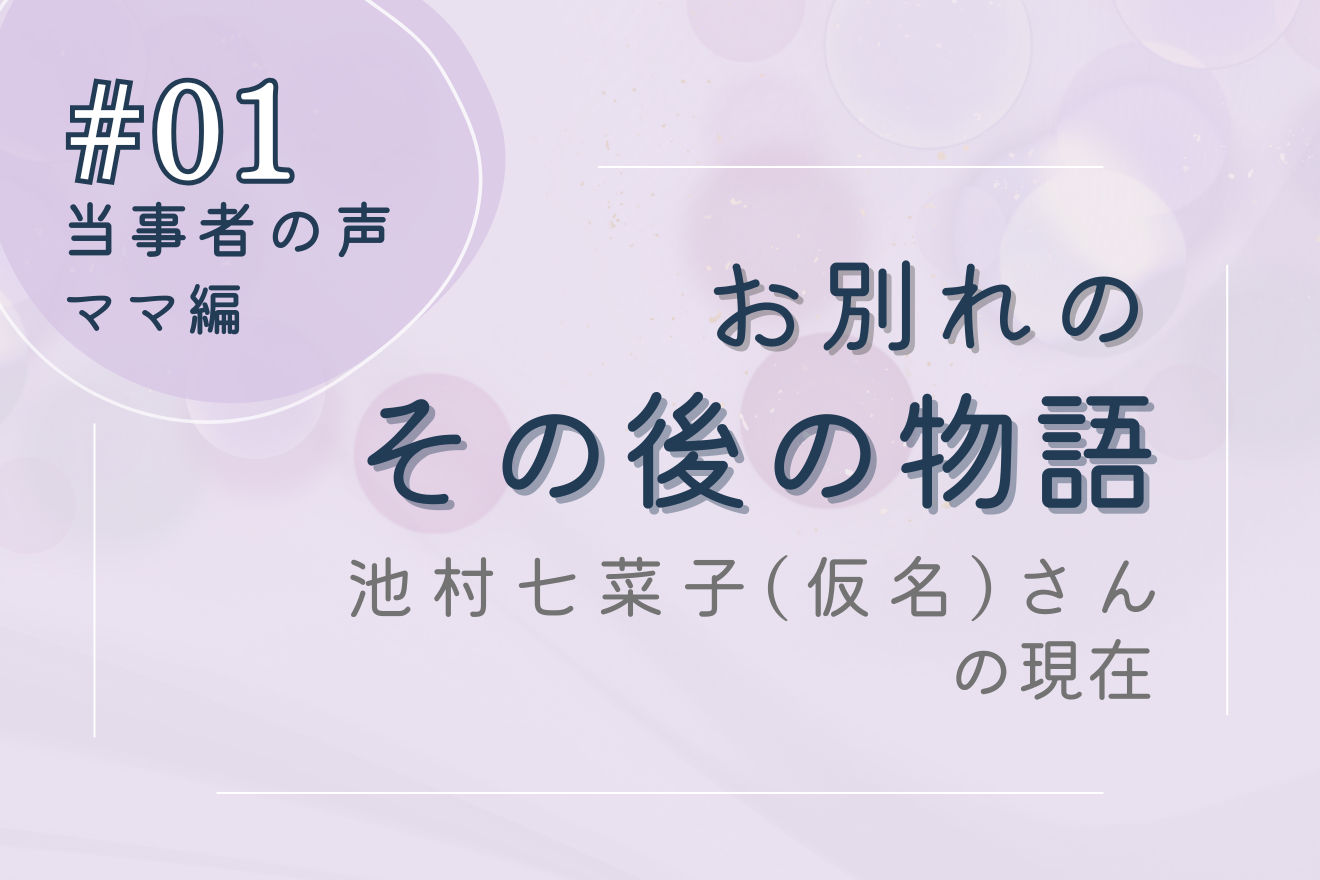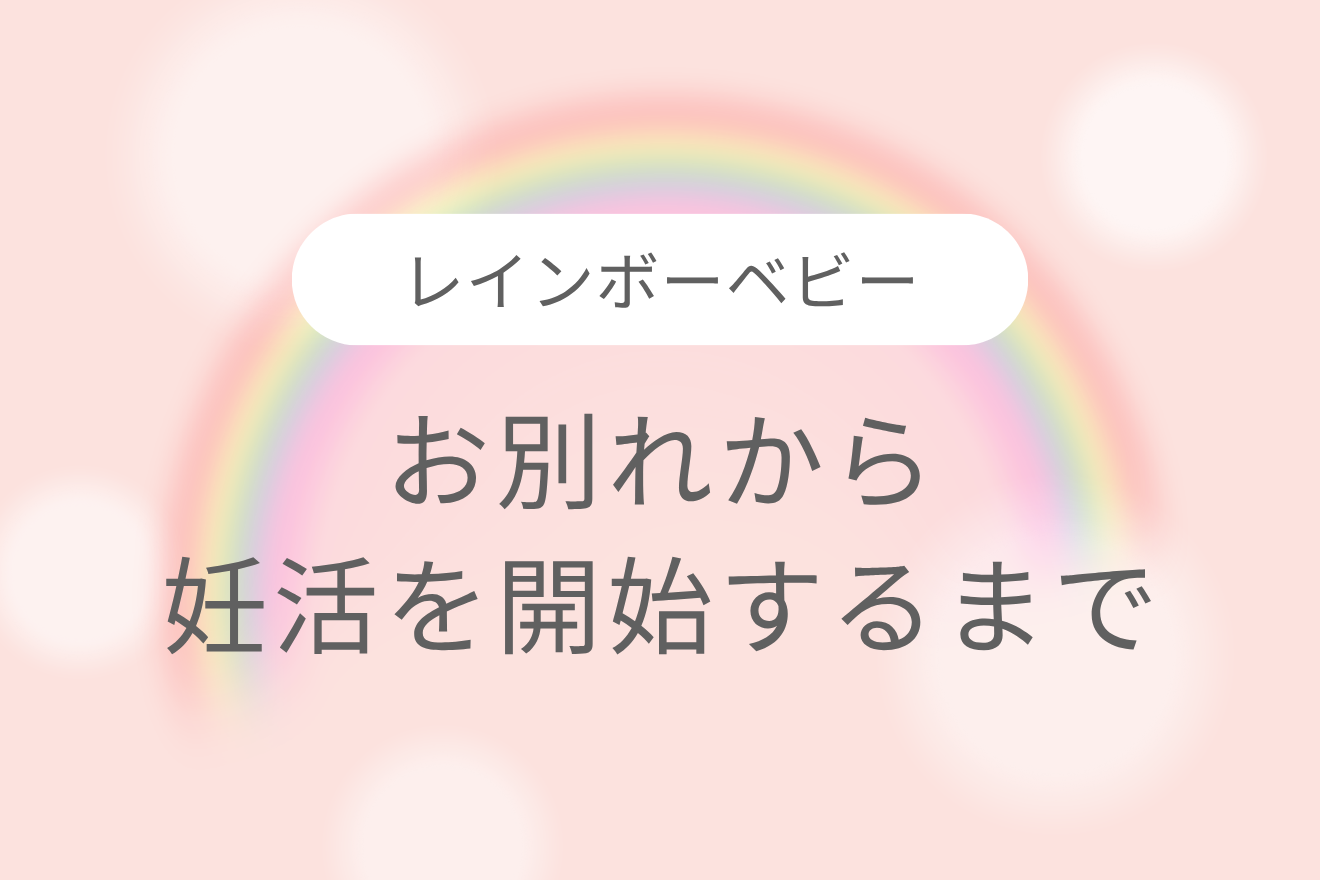人は、大切な人を失ったときに、後悔と自責の念に駆られる。
あの時こうしていれば。どうしてああしなかったんだろう。私のせいで――。
流産や死産は、原因不明であることが多い。しかし、たとえ自分に原因がなくても、悔やむ気持ちが自分を責め立てるのだ。深刻な状態になると、うつ病やトラウマを生じてしまう可能性もあり、周囲のサポートが欠かせない。一方で、赤ちゃんとの死別体験について語ることは、世間一般的にタブー視されることが多い。
私はこの記事を通して、今現在自分を責めているママへ、あなた一人だけでなく同じように悩み苦しんでいるママがいることを伝えたい。そして、周囲の方へ、自分を責めている母親がふと我が子について話したくなったときに、どのように受け止めれば良いのかを一人でも多くの人に知ってもらいたいと思う。
※この先センシティブな画像が含まれます
妊娠37週/常位胎盤早期剥離による死産
名前:小森早紀さん(仮名)
地域:神奈川県
職業:キャリアコンサルタント(契約社員)
家族構成:ママ(36歳)、パパ(36歳)、お子さんがお空に1人、地上に1人(3歳)
32歳で自然妊娠、妊娠37週(妊娠10ヶ月)に常位胎盤早期剥離で死産
「幸せな日々が続くと信じていた」
今回、インタビューに応じてくれた早紀さんは、2018年に結婚(当時30歳)。2020年に妊娠37週(妊娠10ヶ月)で死産を経験している。
常位胎盤早期剝離とは、胎盤が何らかの原因により剝がれてしまい、母子共に重度の障害が残ったり命に関わる重篤な疾患である。また、2023年12月時点で、明らかな原因はわかっていない。今回、早紀さんは当時を振り返り、どんな妊婦にも起こりうる恐ろしい体験について語ってくれた。
初めての妊娠
2019年6月。新緑の色が増す頃。
早紀さんは、第一子となるゆうなちゃんを妊娠した。
夫婦共に、こどもがほしいと望んでいたので、おなかに赤ちゃんがいるとわかったときは心底嬉しかったという。
妊娠中の経過は至って順調。幸いなことにつわりも軽く、仕事も休むことなく続けられる状態であった。上司から体調を心配されるが「大丈夫」と返答し、妊娠9ヶ月まで仕事をこなしていた。
妊婦健診でも、医師から指摘されるような異常は特になかった。このまま仕事も育児も両立して、幸せな家庭を築いていけると信じて疑わなかった。
いつもと違う朝
出産予定日まであと1ヶ月。そろそろ赤ちゃんに会えるのか。
やっぱりどこか他人事のような気がしてしまう。本当に私が母親になれるのかな。
そんなことを考えながら、いつもと同じ朝を迎える。仕事に行く夫を見送り、大きくなったおなかを支えながらゆっくりとリビングのソファに腰をおろす。
「そろそろ入院の準備をしなきゃ」
バッグの中に荷物を詰め始めた時のことだ。
何となくおなかが痛い気がする。臨月に入った時期だ。おなかが痛むことはよくあったので、一度入院準備はやめてソファに横になった。この程度の痛みで病院に連絡するのも迷惑だよなと思い、しばらく休むことにした。
痛い。痛みが強くなってくる。
最初に痛みを感じてからどのくらいの時間が経っただろう。私は、慌てて病院に連絡をした。痛みをこらえながら、電話に出た看護師へ状況を説明する。すぐに病院へ来るように言われたが、こんな状態で電車やタクシーを使い、一人で向かえるわけがない。どうしよう。そんなことを考えている間に、どんどん痛みは何倍にも何十倍にも強くなっていった。
――痛い。痛い。耐えられない。誰か、助けて。
床にうずくまる。
その時の私は、救急車を呼ぶという発想がなく、必死の思いで夫へ電話をかけた。
すぐさまこちらの状況を把握して救急車を呼んでくれた。
瞼の裏で見えたもの
当時の緊迫した状況の中、早紀さんは不思議な体験をしたそうだ。
穏やかな表情でこう語ってくれた。
「救急車が来るまでの間、床にうずくまって必死に痛みに耐え続けました。
ぎゅっと目を閉じている間、一瞬、瞼の裏で赤ちゃんが天に昇っていくのが見えたんです。
スピリチュアルなことはもともと信じない性格なんですが、今思うとあれは、ゆうなが私に最期のお別れの挨拶をしてくれたんだと思います」
医師がこぼした一言
救急車が来た。といっても、ほとんど当時のことは覚えていない。
覚えているのは、バタバタと走る救急隊員。すぐに駆けつけてくれた夫の心配そうな顔。そして、医師がこぼした一言。
「赤ちゃんの心臓が止まっている」
思考が停止した。頭が真っ白になった。
何を言っているの?先生の言葉が理解できない。
だって、ゆうなは今もおなかの中にいるよ。あと少しでママになるんだよ。
そんな私の思いを受け止めてくれる人は誰もいなかった。
出産予定の病院では対応できない状況だったため、再度救急車に乗って大学病院へ運ばれることになった。
大学病院に到着した時には、すでに赤ちゃんの頭が見えている状態だった。吸って吐いて、言われるがままに応じる。大丈夫、きっとゆうなは生きている。先生はああ言っていたけど、生まれたら元気な産声を聞かせてくれるはずだ。そう信じて、おなかの子のためにただひたすらに頑張った。
赤ちゃんが生まれた。産声はない。
生まれてすぐに見えないところに連れていかれた。
「――赤ちゃんは? ねぇ、赤ちゃんはどうなったの?」
私は、答えが返ってこない問いを繰り返し叫んでいた。
意識が朦朧として、目の前が真っ暗になっていった。
母親になった瞬間
次に目が覚めたのは、機械だらけの無機質な部屋。白くて、冷たくて、怖い。
口に何かが入っていて声が出せない。体のあちこちが痛い。ぼーっとする。
看護師さんが体を拭いてくれた。私や赤ちゃんの状態は教えてくれない。
おそらく、ここはICU(集中治療室)だ。大量出血で命の危険がある状態だったのだろう。しばらくして家族が来た。夫と母の表情を見て、悟った。赤ちゃんはもう亡くなったんだ。
涙が溢れた。声も出せない状態で、静かに泣くことしかできなかった。
数日が経過し、状態が良くなったのでMICU(母体胎児集中治療室)へ移動することになった。
ようやく、ゆうなに会える。ゆうなと対面した時に、自分がどんな感情になるのか不安だった。早く会いたい気持ちでドキドキと胸が高鳴る。
――可愛い。
初対面なのに、顔を見ただけですぐにわかる。この子は私の子だ。
抱っこをした瞬間に、初めて自分が母親になったのだと実感した。隣で夫が微笑んでいる。
ああ、ようやく家族になれたね。生まれてきてくれてありがとう。夫婦揃って何度も、可愛いねと繰り返した。
そして、同時に後悔の気持ちが押し寄せてきたのであった。

つのりゆく後悔の気持ち
早紀さんは、退院してからの生活を「人生のどん底」だったと語る。
体は徐々に軽快していったが、心は追いつかない。
100人に1人の確率と言われているのに、何で私だったんだろう。
原因は何?私が悪かったの?
答えのない問いをぐるぐると繰り返す。やがて、感情がコントロールできなくなった。
勝手に涙が溢れる。安産祈願なんて意味がなかった、と神様へ怒りが向く。
私の気持ちなんて誰にもわかるはずがない。何も信じられない。食欲もなくなり、夜も眠れなかった。その一方で、徐々に日常に戻ろうとしている自分に気付き、ゆうなに申し訳なくなった。
そういえば、妊娠34週の妊婦健診の時に、血圧が普段より少し高いことを指摘されていた。あの時「赤ちゃんが順調に育っているなら大丈夫だろう」と甘く考えたのが悪かったのかな。妊娠中に、大好きなラーメンを食べたのが悪かったのかな。ゆうなへ話しかけたりお腹を撫でてあげればよかったな。仕事も休めば良かった。ごめんね、ごめんね。
――まさしく、人生のどん底だった。
一緒に泣いてくれる人
そんな当時の早紀さんを救ってくれたのは、古くからの友人たちだった。
仲の良い友人には今回の経緯を伝えよう、と勇気を振り絞って連絡を取った。親友は、白い花束を携えてすぐに会いに来てくれた。
早紀さんは当時について、こう語る。
「親友には、本当に感謝しています。自分を追いつめて苦しんでいた時に、話を聞いて一緒に涙を流してくれたことは、あの時の私にとって一筋の光のように感じました」
心を許せる相手に自分のありのままの状態を話すことで、心が整理されたそうだ。悲しみの感情を表へ出すことが、心を軽くする第一歩になる。誰かに話すことは、大きな意味があることなのだ。
前を向いて歩く
Reva Rubin(*1)は母性論で、「妊娠期間中からこどもに対する愛情の絆が育つ」、また「死産はその関係の拡大と更なる発展を終了させるが、既に達成した絆は消去できない」と述べている。
たとえ生まれたときに亡くなっていようと、母親からすれば「長い期間を共に過ごした愛おしい我が子」なのだ。お別れした赤ちゃんを存在しないものとして扱うのではなく、存在を認め、たしかに赤ちゃんを産んだ母親であると認識した上で関わる必要がある。
早紀さんのご友人は、早紀さんのことを「ゆうなちゃんを産んだ母親」として接した。その上で、別れを悲しみ共に涙を流してくれたため、早紀さんの心が軽くなったのだろう。
早紀さんは、最後にこう語った。
「苦しさを一人で抱え込まないでほしい。あなた一人だけでなく、同じように悩み苦しんでいるママがたくさんいる。焦らずゆっくり自分のペースで、心と体を整えてほしい。いつかきっと、前を向けるときが来るから――」
私は、赤ちゃんとのお別れを経験した母親が自分を責めたり後悔したりすることを、赤ちゃんに対する愛情表現だと感じている。それだけ大切に思ってもらえて、赤ちゃんはきっと幸せに感じているに違いない。
どん底から抜け出せない時は、自分の感情を吐き出せる方法を見つけて、気持ちを表に出すことが大切だ。それを気兼ねなくできるような、優しい世の中になっていくことを願っている。

(写真=早紀さん提供/取材・文=SORATOMOライター 小野寺ゆら)
*1 米国のピッツバーグ大学大学院母性看護学の教授。母親役割獲得過程など多くの概念モデルを定義している。
この記事は、2023年12月に取材した際の情報で、現在と異なる場合があります。
当事者の経験談を元に構成しており、同じお別れを経験した方に当てはまるものではありません。
不安な症状がある場合は、医療機関の受診をおすすめします。
※記事内の画像や文章の転用を禁じます